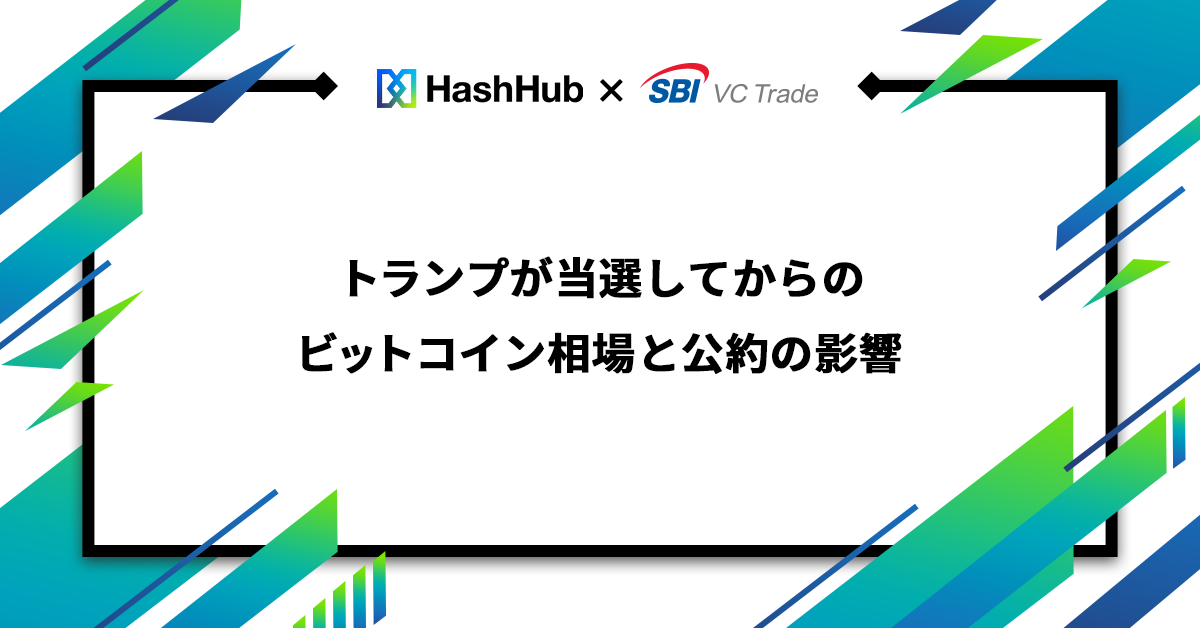▼目次
本記事は2024年11月12日に執筆されています。
前提
本レポートでは、先の米国大統領選挙でドナルド・トランプ(以下トランプ氏)が当選してからの、ビットコイン(BTC)相場について、筆者の雑感を纏めます。
本レポート執筆の11月12日時点においては、ビットコインはトランプ氏が当選してから約30%の上昇を見せています。
出典:https://www.google.com/finance/quote/BTC-JPY?sa=X&ved=2ahUKEwj1jIP9yNaJAxUSaPUHHcfFErUQ-fUHegQIDBAf
価格が高騰している時、マーケット参加者の多くは、ビットコインはデジタルゴールドであり、限りある準備資産だと認識して、買いが買いを呼ぶ一方的な展開になる傾向にあります。反対にベア相場においては、そのような価値としては認識されず、一方的な売りになります。
今は典型的なブル相場で、供給がタイトなビットコインに対してマーケット参加者がFOMO(Fear of Missing Out)の感情で、我先にと、ロングポジションを構築しています。
ドナルド・トランプのビットコイン関連の公約と予想される影響
トランプ氏の2024年選挙キャンペーンでは、暗号資産の規制緩和と推進が重要な公約として掲げられています。トランプ氏は、バイデン政権や民主党が進める厳格な暗号資産規制に対抗し、「暗号資産の大統領」として、規制の緩和とビットコインの支持を約束しています。具体的には、以下のような政策を挙げています。
1. ビットコインの備蓄
米国政府がビットコインを保有し、デジタル資産の導入を加速する考えを示しています。
参考:Cointelegraph
2. 暗号資産に特化した諮問委員会の設立
暗号資産業界からの意見を政策に反映させるための組織を設ける予定です。
参考:POLITICO
3. SEC(証券取引委員会)の改革
暗号資産に対して強硬な姿勢を示すゲイリー・ゲンスラー現SEC委員長の解任と、暗号資産に友好的なリーダーの起用を公約しています。
参考:POLITICO
4. 中央銀行デジタル通貨(CBDC)への反対
連邦準備制度が独自のデジタル通貨を発行することに反対し、暗号資産の分散性を支持しています。
参考:POLITICO
トランプ氏の暗号資産支持の姿勢は、彼がかつて暗号資産に批判的であったことから大きく転換したと見なされていますが、近年は共和党の多くが暗号資産に支持を示し、トランプ氏も選挙活動の一環として積極的に取り組んできました。この方針は、暗号資産を重要なテーマとする有権者層へのアピールとして位置づけられています。
また、トランプ政権の組閣に先立ち、11月12日にルミス上院議員は、アメリカ政府が5年間で合計100万ビットコイン(BTC)を購入するため、毎年20万ビットコインを購入するという法案を提案しました。
引用:https://x.com/BTC_Archive/status/1856085189916512552
発表当日の現在の価格で計算すると、その価値は870億ドル(約13.4兆円)に相当します。
現在の議会では、民主党からの支持が必要であり、この法案が通過するかは不透明で、実際に議論が本格化されるのは、トランプ氏が大統領に就任して議会も入れ替わってからではないかと筆者は予測しているものの、それでもアメリカ政府がビットコイン(BTC)を備蓄するシナリオが現実味を帯びてきたことは間違いありません。
各国の政府や中央銀行にとって、米国債以外の最も主要な準備資産は金(ゴールド)ですが、各国の中央銀行の金保有残高にはそれぞれ差異があります。
例えば以下の通りです。
・アメリカ:8000トン
・ドイツ:3000トン
・中国:2000トン
・日本:800トン
この差異は歴史的経緯がありますが、数字を見てのとおり、今から日本が金保有量で上位国に追いつくのは困難です。
これから10年、あるいは数年で、ビットコイン(BTC)も準備資産となる過程で、各国の備蓄差は埋めがたい開きが出そうです。
そして相場の観点では、10兆円相当レベルの資金流入は過去に例がなく、実現すると相当なレベルでビットコインの価格を押し上げることは間違いありません。これがFOMOの一番の要因となっています。
ゴールドの価格が下落している要因
気になるのは、トランプ氏当選後の、ゴールド価格の下落です。株・ビットコイン(BTC)の相場に対してひたすらに売られており、過去2ヶ月の上昇を吐き出しました。
出典:https://www.google.com/finance/quote/GLD:NYSEARCA?sa=X&ved=2ahUKEwjjsrvAydaJAxWravUHHUnKBdQQ3ecFegQIVhAf
ゴールド価格の下落要因は恐らく以下のようなものだと筆者は推察しています。
・長期金利の上昇。金利がつかない資産の売り。
・トランプ氏が大統領になると、中東やウクライナの情勢が改善するかもしれない。地政学リスク要因で買われていたシナリオの巻き戻しが必要かもしれない。
・トランプ氏はロシアの米国資産を凍結解除するかもしれない。凍結されない資産としてゴールドが買われていたが、このシナリオの巻き戻しが必要かもしれない。
・ビットコインが新たな準備資産として買われている。金利を生まないオルタナティブアセットを、ポートフォリオのうち何パーセント配分できるか?これは人によって10%とか20%、せいぜい30%くらいまでが一般的な投資家だと考えられる。その限られたアロケーションの中で、ゴールドの時価総額がビットコイン(BTC)に吸収されているのではないかと推察しています。
筆者は、ビットコインもゴールドも、どちらの保有も勧めてきて、自身もそのようなポジションを構築してきました。今でも米国の財政問題などは変わらずゴールドのシナリオは維持していますが、随時シナリオの点検は必要だと緊張感を感じる1週間の値動きだと言えます。
場合によっては今後もレポートで取り上げます。
台頭する米国株の成長鈍化シナリオ
米国株の成長鈍化予測が支持を得ていることもその一つです。実際に成長鈍化するかではなく、その可能性を考える人が多くなっているという認識です。典型的な例では、ゴールドマン・サックスは、S&P500種株価指数の今後10年の収益率が、年率で3%と過去10年の4分の1にとどまるとのリポートを発表しました。
参考:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN21C2O0R21C24A0000000/
これまで米国株の上昇をけん引したのは、GAFAなどの大型テックを含む、S&P500指数全体時価総額の36%を占める上位10銘柄です。彼らは「上位銘柄の株価収益率の高さは、2000年前後のドットコムブームのピーク時以来最も高い水準にある」と指摘しています。
株式相場上昇がこうした上位銘柄に集中してきたことが、今後の米国株の収益率の伸び悩みにつながるとしている。上位銘柄の企業が増収と利益率上昇を長期間維持することは極めて困難であるとして、いずれは収益の伸び鈍化に合わせて収益率も小さくなると見込みます。
GDPの伸び率低下も懸念材料といいます。レポートでは、今後10年間にGDPが4四半期にわたりマイナス成長になるとの予想を示しました。
実際に現在S&P500の予想PERは22倍で、過去平均と比べて割高となっています。またインフレと金利高が継続する可能性も指摘されています。金利高はPERの拡大を正当化しにくくする要素です。インフレ再燃・金利高騰となると株の割高感はより意識されやすくなります。
この割高感が意識されると、PERやEPSなどがなく、モメンタムのほうが価格決定要因になりやすい暗号資産(特にビットコイン)を買おうかという動機が強まります。
総括
本レポートでは、ドナルド・トランプが当選してからのビットコインについて筆者の雑感を纏めました。
現在、ビットコイン(BTC)のモメンタムはとてつもなく高まっていて、投資家の資金アロケーションを後押しする要素が多くあります。筆者は、2024年後半は強気なシナリオを提示しており、こちらでもその要素は解説しています。
関連レポート:2024年下期に向けたBitcoinへの投資スタンス
今の状況は、適切なリスク管理をしながら、マーケットに向き合う絶好のタイミングと言えるでしょう。
【ご注意事項】
本記事は執筆者の見解です。本記事の内容に関するお問い合わせは、株式会社HashHub(https://hashhub.tokyo/)までお願いいたします。また、HashHub Researchの各種レポート(https://hashhub-research.com/)もご参照ください。
提供:HashHub Research
執筆者:HashHub Research