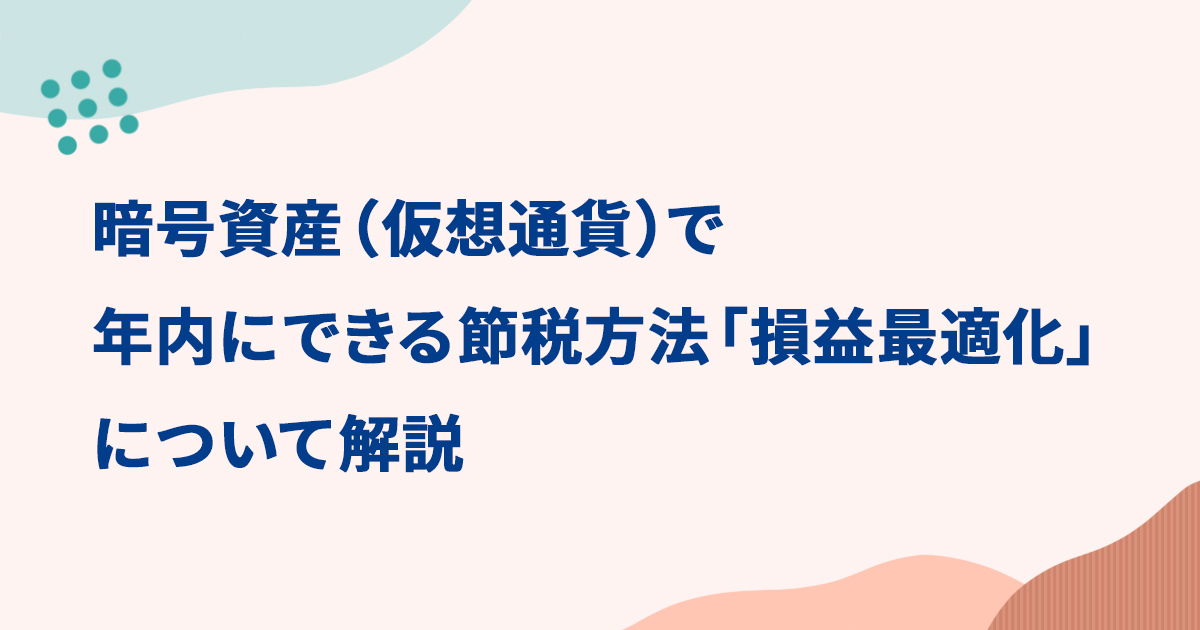▼目次

暗号資産(以下、仮想通貨)取引をしていると、利益が出たときはもちろん、損失が出たときも確定申告の必要性を考えなければなりません。とくに年末が近づくと、税金対策として、今すぐにできることを検討する方も多いのではないでしょうか。
そこで、黒字に転じる可能性が低い含み損の仮想通貨の損失を確定させてしまい、所得を小さくする「損益最適化」という節税方法が年内にできる方法としては特に効果的です。場合によっては確定申告そのものが不要になるかもしれません。
この記事では、損益最適化の基本や、実際にどのような判断をすれば効果的な節税につながるのかを解説します。少しでも税金を少なくしたいとき、ぜひ参考にしてください。
仮想通貨の税金対策にはどんなものがある?
個人投資家が実践しやすい仮想通貨の税金対策には、次のようなものが挙げられます。
● 年内の利益を20万円以下に抑える
● 売却せず保有のみにする
● 雑所得同士で損益通算をする
● iDeCoやふるさと納税などを活用する
給与所得者の場合、年内の利益を20万円以下に抑えれば、確定申告そのものが不要になります。
仮想通貨を売却したり決済に使ったりせず、保有しているだけなら利益は確定しません。つまり「ただ持っているだけ」であれば課税されないので、その年の確定申告を避けるためにあえて保有のみに留めておくのも、有効な節税対策になるでしょう。
また、仮想通貨で損失が生じたときは、同じ「総合課税の雑所得」の所得から相殺することも可能です。これを「損益通算」といいます。たとえば「仮想通貨の損失を副業の収益から差し引く」「イーサリアムの損失をビットコインの利益で相殺する」といった例が挙げられます。損益通算することで、全体の課税所得を減らせるでしょう。
さらに、iDeCo(個人型確定拠出年金)やふるさと納税によって、所得からその掛金や寄付額を差し引く「所得控除」も、仮想通貨の利益による税負担を間接的に抑える手段となります。
含み損・含み益があるときに活用できる節税方法「損益最適化」のやり方
上記で解説したように、節税するには仮想通貨の損失や利益を調節して、課税される所得を少なくするのが有効です。この節税方法を「損益最適化」といいます。ここでは、損益最適化の流れを紹介します。
1.損益を正確に算出する
仮想通貨取引を行う際には、「含み損益」と「実現損益」を正確に把握することが重要です。実現損益はすでに確定しているため課税対象となりますが、含み損益はまだ確定しておらず、課税対象にはなりません。
とくに、複数の仮想通貨(例:ビットコイン、イーサリアムなど)を取引している場合や、複数の取引所(例:取引所Aと取引所B)を利用している場合は、それぞれの損益を個別に整理しておくことが大切です。
Gtaxのような損益計算ツールを利用することで、損益最適化を効率よく行いやすくなります。
2.利益がある場合は含み損を確定させる
仮想通貨取引で利益が出ている際は、含み損のある仮想通貨を売却して損失を確定させることで、課税対象となる所得を減らせます。利益は減りますが、そのぶん課税額も軽減され、結果的に節税につながります。
【シミュレーション例】
・全体で700万円の利益が出ている
・1通貨あたり150万円で購入した仮想通貨Aを、1通貨80万円で5通貨売却
・利益700万円 - 損失350万円 = 利益350万円
このシミュレーションでは、含み損を確定させることで全体の利益が700万円から350万円に圧縮されます。その結果、課税対象額が減り、支払う税額の軽減が見込めます。
3.赤字の場合は利確して利益を圧縮する
赤字の場合は、含み益のある仮想通貨を売却して利益を確定させることで、損失と相殺して課税対象額を減らすことができます。相殺することによって、その年の実現損益がゼロまたはマイナスになれば、確定した利益分に税金がかからなくなります。
たとえば、仮想通貨取引で「利益が10万円」発生している場合、そのままでは10万円が課税対象となります。しかし、「損失が6万円」あれば、それを相殺することで課税対象額を実質4万円に抑えることができます。このように、損失を活用することで税負担の軽減が可能です。
ただし、利益より損失額が大きい場合、課税対象は0円になりますが、超過した損失分は翌年に繰り越すことができません。そのため、含み益を確定させるタイミングを慎重に判断することが重要です。
4.翌年以降も保有したい銘柄は含み損益を確定後に買い戻す
翌年以降も保有したい銘柄がある場合は、売却後すぐに買い戻すことで再度保有できます。この手法を使うと、保有量を維持しつつ、節税対策を進めることが可能です。
節税対策をするためには、実現損益をつくり出す必要があります。そのため、「含み損益」を一旦売却して損益を「確定」させるのです。売却後すぐに同じ銘柄を買い戻すことで、保有量は変わらず、その銘柄を引き続き持ち続けられます。
この方法により、その年に確定した損失を利益と相殺して課税額を軽減できます。また、買い戻した際の価格が新しい取得価格となるため、今後の売却時に発生する損益の計算もリセットされます。
「含み損益を確定後に買い戻す」というのは、税金対策として損益を確定しつつ、同じ銘柄を保有するためのテクニックです。特に含み損を抱えている場合、課税額を抑えられるでしょう。
ただし、所得の計算方法に総平均法を用いている場合、新たに購入することで売却した通貨の損益も変化してしまうため、注意が必要です。
含み益・含み損を翌年に持ち越すか、どう判断するべき?
損益最適化するうえで、「翌年に持ち越した方が良いかも?」と考えている方もいるかもしれません。
仮想通貨取引では「損失繰越の禁止」ルールがあり、赤字が発生した場合でも翌年に繰り越すことはできません。そのため、今年中の赤字が確定してしまった場合は、可能な限り含み益を確定して、その年の損益を相殺するのが有効です。
たとえば、年末に赤字が10万円発生している場合、そのままでは税金上の効果を得られません。しかし、含み益を10万円分確定させて赤字と相殺すれば、課税所得をゼロにでき、余分な税負担を抑えられます。反対に、含み益をそのまま翌年に持ち越してしまうと、翌年は利益がそのまま課税対象となり、節税効果を享受できません。
したがって「赤字を今年中にどう活用するか」が重要なポイントとなります。含み損がある場合は今年中に損失を確定させ、含み益がある場合も赤字との相殺を視野に入れて計画的に利確することを検討しましょう。
まとめ
仮想通貨取引の税金対策には、「損益最適化」をはじめとするさまざまな方法があります。含み損を確定して利益を圧縮する、含み益を確定して損失と相殺するなど、その年の実現損益を調整することが節税のポイントです。Gtaxのような損益計算ツールを活用することで、専門的な知識がなくても簡単に実施することが可能です。
とくに日本では、損失の翌年繰越が認められていないため、赤字が発生している場合は年内に損益を調整することが節税につながります。また、翌年も保有を続けたい銘柄がある場合は、一旦売却して損益を確定した後に買い戻すことで、課税額を抑えつつ保有を継続できます。
適切な節税対策を行うためには、損益を正確に把握し、取引タイミングを計画的に調整することが不可欠です。損益計算ツールなどを活用しながら正確に計算し、できる限りの節税対策を講じてはいかがでしょうか。

【ご注意事項】
本記事は執筆者の見解です。本記事の内容に関するお問い合わせは、株式会社Gtax(https://crypto-city.net/)までお願いいたします。
また、Gtaxホームページ内の各種コラム(https://crypto-city.net/media)もご参照ください。
執筆者:藤村 大生
株式会社Gtax 取締役
税理士・公認会計士
株式会社Gtaxにて暗号資産投資家の確定申告サポート、暗号資産事業者への経理支援を担当。暗号資産会計・税務に関する深い知見を有する。監査法人ではデューデリジェンスや原価計算導入コンサルティングに従事し、証券会社監査チームの主査として分別管理に関する検証業務も経験。