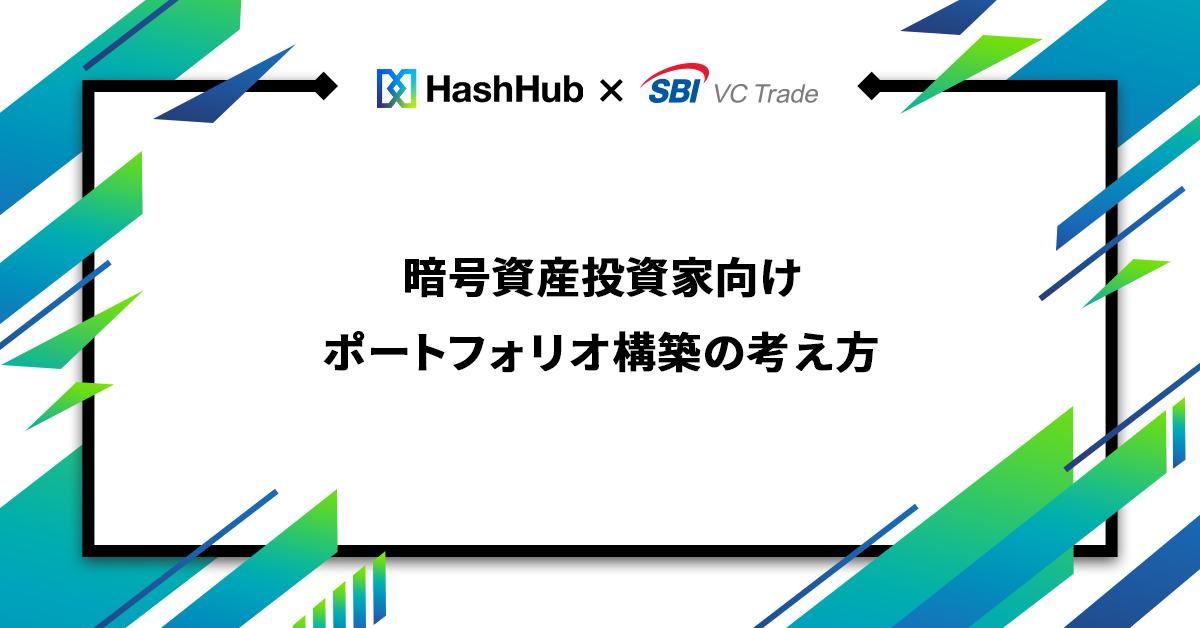▼目次
前提
本レポートでは、暗号資産投資家にとってポートフォリオ構築の考え方、株式と暗号資産(仮想通貨)のバランスのさせ方について筆者の視点で論じます。
暗号資産投資家にとって資産ポートフォリオの何%を暗号資産にするかは時折議論になるテーマです。恐らく一般的なストラテジストや金融専門家がこの疑問を投げかけられる際の回答は、暗号資産に前向きな人物でも「ポートフォリオの1-3%程度が適切」といった回答をするのではないかと思います。
一方でX(旧Twitter)の暗号資産ユーザー界隈では、資産の5割以上、多い人は8割以上が暗号資産になっているという人も少なくありません。または初めての投資が暗号資産で、そのまま資産額が膨らみ、株式などとバランスを取れていないという人もいるだろうと想像します。
暗号資産投資家にとって適切なポートフォリオの割合は?株式と暗号資産のバランスのさせ方は?この疑問に絶対的な回答はありません。さらにシンプルな問いとして、集中投資と分散投資どちらが優れている?というような問いですら、絶対的な回答はないのがポートフォリオマネジメントです。
ですが、今回は筆者の視点で株式・暗号資産・その他アセットクラスのバランスのさせ方について論じてみたいと思います。筆者は暗号資産というアセットクラスに対して10年以上関わってきて、その間基本的に自身でも保有を継続し、今時点においても暗号資産の価格形成に期待しています。
関連レポート:2024年下期に向けたBitcoinへの投資スタンス
関連レポート:2024年下期に向けたEthereum (ETH)への投資スタンス
そのうえで株式や不動産、その他のコモディティも保有しています。これらのポートフォリオに対してどのような考えを持っているか述べてみます。
基本的な考え方
1.アセットクラスは分散
筆者の基本的な考え方として、特定のアセットクラスに例えば80%以上の資産を投資することは基本的に望ましくないと考えています。理由の1つは、他の大きな機会があった場合にそれを取り逃してしまう可能性が高いからです。例えば暗号資産に集中投資していた場合、昨年から今年にかけてのAI相場のリターンを米国株式市場から得られていません。ドットコムバブルを彷彿させるとも揶揄されるラリーを取り逃しています。アセットクラスの集中が望ましくないと考える理由に、ダウンサイドリスクを全て引き受けてしまう可能性があるからです。暗号資産に資産の全てを集中させていた場合、2021年のような下落相場では大きな損失になります。
一方で、アセットクラスへの集中が望ましくないのは、基本的にはという枕詞がつき例外ケースもあります。筆者もある時期には暗号資産を90%以上の比率で保有していた時期もあり、その期間には大きなリターンを得ています。この例外ケースは後の節で後述します。
2.世界の資産形成の主流は米国株式
いくら暗号資産に強気でも、個人の資産形成の主役はやはり株式です。そして世界の株式市場の60%は米国株です。つまりポートフォリオに米国株式のインデックスを組み込んでいなければ、平均的リターンから大きく乖離する可能性があります。
そういった観点で筆者は、平時は米国株が60%程度になっているのが、基本の枠組みです。この割合は増減する可能性もありますが、買い持ち資産の60%が米国株式になっていない場合は、平均と乖離する自覚を持ってポジションを取るときです。
2024年はポートフォリオの20%程度の割合が暗号資産で推移していました。この割合は暗号資産ユーザーにとっては少ないと感じるかもしれませんが、グローバルマクロの観点にたったポートフォリオマネジメントとしては極めて大きい買い持ちポジションです。
しかしながら2023年から2024年にかけて米国株式市場と暗号資産市場は相関が薄れていますので、ビットコイン(BTC)が10%近い暴落をした日においても、ビットコインがポートフォリオの20%ならば全体でのマイナス寄与度は2%で済み、その間に株式のリターンがマイナスを相殺することもありえます。
基本的には6割程度の米国株式ポートフォリオがあって、そこに個人の趣向やリスク感応度で他のアセットクラスが組み込まれるべきというのが私の考えです。
3.コアサテライトとアルファを探すリサーチ
保有する米国株式と暗号資産のうちの70%程度はインデックスです。暗号資産に関してはビットコイン(BTC)それ自体が暗号資産市場の成長に賭けるインデックスとして扱っています。
コアサテライトとは、保有する資産をコア(中核)部分とサテライト(衛星)部分に分けて考え運用することを指します。コア部分は長期かつ安定的に運用し、サテライト部分はコア部分よりも高いリターンを求めて積極的に運用する考え方で、コア部分とサテライト部分をバランスよく保有することで、資産全体としてのリスクやコストを抑えつつ、市場平均よりも大きいリターンの確保を目指すというものです。
コアはS&P500などのインデックスになります。今回のケースであれば60%のうちの70%です。これは組み込んだらほったらかしです。
しかし時間とリスクを十分にかけるのは残りのサテライト部分です。サテライトですが、リサーチとリスクテイキングは全てここに集中することでアルファを生みます。
今年前半の旬のセグメントはいくつかありましたが、例えば半導体とビッグテック中心のAI・日本のバリュー株・暗号資産であればエアドロップを期待するDeFi運用がありました。あくまでコアの70%を確保した状態でこれらにしっかりリサーチ時間を投下して、サテライトの範囲でリスクテイキングすることで、例え失敗しても市場平均のリターンから大きくは下振れ乖離することなく、アップサイドを狙えます。
60%の米国株式のうちの3割を3銘柄に集中させてもそれぞれポートフォリオ全体の6%になりますし、20%のうち全体の2割をある銘柄に集中させてもポートフォリオ全体の4%となり、これらは個別銘柄のリスクテイキングとしてそれなりに大きく、成功した場合はポートフォリオへの利益寄与度は決して小さくありません。
アセットクラスの集中が正当化されるケース
さてここまで筆者自身のポートフォリオマネジメントの考え方について述べてきました。ある程度バランスの取れた論理かと思います。これらのバランスの取れたポートフォリオは、ある期間を切り取れば特定の集中投資には劣後します。特に現代では、X(旧Twitter)を覗くと、「全財産ビットコイン」「全財産SOXL」「全財産レバナス」という人も存在して、それらの銘柄が上昇した日にはそれらのアカウントの投稿が非常に羨ましく思いますが、重要なのはリスク調整後リターンであり、リスク調整後リターンで市場平均を上回ることが理想的です。そういった観点で、基本的に集中投資は望ましいものではありません。
一方で、アセットクラスの集中が正当化されるケースも非常に少ないものの場合によってはありえます。結局、投資とはその人の年齢・仕事・手持ち資金によって違うのです。
私は数年以上前に、20代のある時点でポートフォリオのかなりの割合が暗号資産でしたが、これは教科書的には全く褒められた選択ではありませんでした。しかしながらその当時は、以下の条件が揃っていました。
①私が20代で若く、ライフステージとしても損失がフラストレーションではなかったこと
②投資元本も決して大きくはなかったこと
③私は事業運営する能力もあり、仮に全損しても、その他の収入から回収可能だったこと
④当時、暗号資産(仮想通貨)黎明期で期待値が大きかったこと
結果的にこのアセットクラスの集中は幸運にも報われたわけですが、これは特殊なケースです。今の筆者では、よほど大きな機会を見つけた場合において、コアサテライトのサテライト部分を時に引き上げることはあっても90%の集中投資は正当化されません。
しかしながら、ここで説明したいことはアセットクラスの集中が正当化されるケースも場合によってはありえるということです。若くて頭が良く、かつ瞬発力を備えた人物においては、Bot運用やイベント運用、DeFi運用などで機会を見出すことで、暗号資産は依然として優れた集中投資先として合理化される可能性があります。しかしそれはあくまで少数の人にあてはまるケースです。
総括
本レポートでは、暗号資産投資家にとってポートフォリオの構築の考え方、株式と暗号資産(仮想通貨)のバランスのさせ方について筆者の視点で論じました。
冒頭で述べた通り、このテーマに正解はありませんし、あくまで筆者の考えです。しかしながら暗号資産ユーザーは、本格的な投資が暗号資産が初めてで他のアセットクラスとのバランスの取り方を試行錯誤していたりするケースや、昨今のNISAなどで投資の多様化を検討しているケースもあるでしょう。考え方の一つとして参考になれば幸いです。
【ご注意事項】
本記事は執筆者の見解です。本記事の内容に関するお問い合わせは、株式会社HashHub(https://hashhub.tokyo/)までお願いいたします。また、HashHub Researchの各種レポート(https://hashhub-research.com/)もご参照ください。
提供:HashHub Research
執筆者:HashHub Research