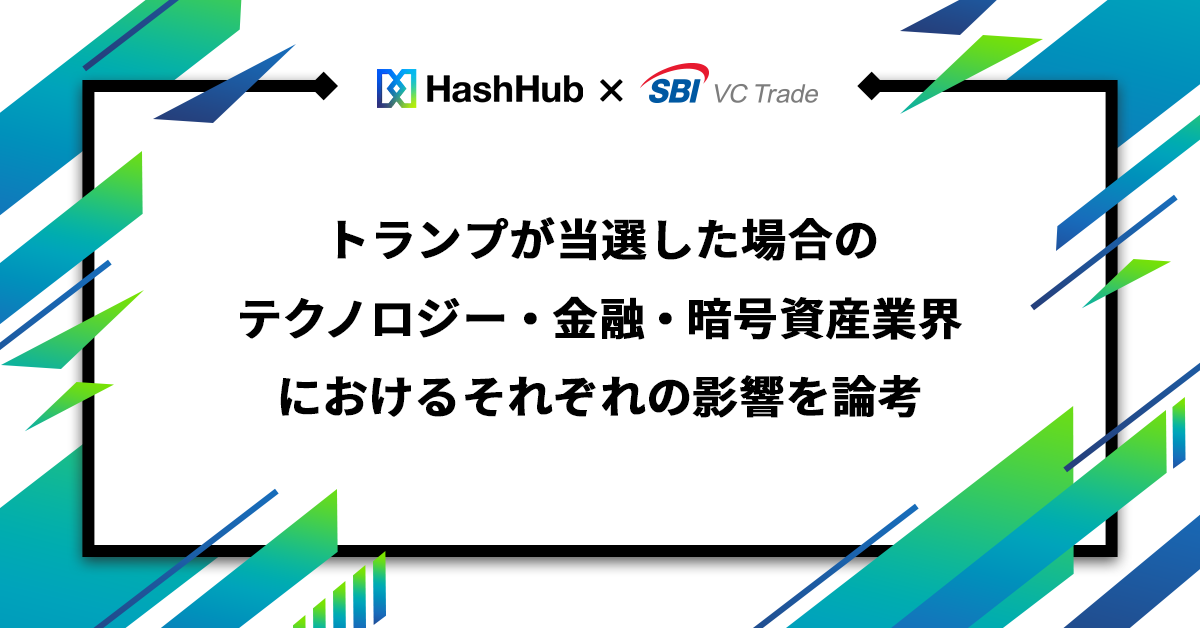前提
ドナルド・トランプ前大統領が、7月13日に東部ペンシルヴェニア州バトラーでの支援者集会で演説中に暗殺未遂され、その後同氏が力強さを見せたことで、トランプ氏の当選確率が高まっています。
本レポートを執筆している時点の世論調査では、トランプ氏支持率はバイデン大統領を2ポイント上回るに留まりますが、予測市場ではトランプ当選に対してより大きく見込んでいます。また、株式市場ではトランプ当選を見込んだトレードも行われるようになっています。
今回は氏が当選した場合における影響を、HashHub Reserech読者が関連性が高いであろうテクノロジー業界全般・金融業界全般・暗号資産(仮想通貨)業界全般に対してシナリオ分けを試み、筆者の私見を織り交ぜます。
【関連:おすすめレポート】
2024年米国大統領選挙がビットコイン(BTC)の価格・相場に与える影響を解説
テクノロジー業界全般
最近になってトランプはテクノロジー業界の支持を強力に取り付けています。代表的な人物としては、イーロン・マスク、ピーター・ティール、a16zの創業者、オラクルのCEOなどです。また副大統領候補に指名されたバンスは、ベンチャーキャピタリストのキャリアを持っています。彼はピーターティールのファンドで働いていた経歴を持ちます。
トランプが大統領になった場合、テクノロジーセクターへの影響はポジティブに見られますが、実際には状況はより複雑です。米国の株式市場で相当部分を占めるテクノロジー企業の代表格であるGAFAへの風当たりは強いです。今回の選挙で、ビッグテックの幹部は完全に静観していますが、やはりこれらの企業のイメージは民主党寄りのイメージを持ちますし、トランプと良い関係を築くには若干のハードルがあるだろうと考えられます。
加えて副大統領候補のJ・D・バンスは、テクノロジー業界出身でも、ビッグテックの解体を支持する人物です。ビッグテックがより小規模のベンチャーの競争を阻害していると言います。トランプがこの考えを取り入れた場合、相当な波乱が想定されます。これらを考慮した場合、テクノロジー業界にはポジティブな影響もあれば、ネガティブな影響もあるというのが実際であると言えます。
GAFA解体(特にやり玉にあげられるのがGoogle親会社であるAlphabetです)が実際の争点になった場合、リアクションとしては株価に相当な影響があり、おそらく下落リアクションが起きるはずです。時価総額が巨大なだけにマーケット全体にインパクトがあるでしょう。
ただし過去にAT&Tが分割された事例に学ぶのであれば、分割されたとしても、企業のファンダメンタルズを完全に破壊するものでもなく、また株主資本を必ずしも毀損するものでもありません。AT&Tの場合は、分割後の持ち株は、元のAT&Tの株式に基づいて、7つの地域会社(Ameritech、Bell Atlantic、BellSouth、NYNEX、Pacific Telesis、Southwestern Bell、US West)の株式として配布されました。株主は分割後の各企業の株式を受け取り、元の投資価値を保ちながら新しい成長機会にアクセスできるようになりました。これらの企業はその後、買収などもされていますが、配当込みで平均8-9%を実績ベースで生み出しました。
筆者は個人的に5-10年程度の時間軸で見れば、ビッグテックの分割は米国民の世論も追い風となり、実行される可能性は少なからずあると考えています。AT&Tの事例を見ても、米国産業界に人材と資源の流動性をもたらしたことは事実であり、投資家も一定のリターンを得られたことも踏まえると、どこかの時点で受け入れる未来なのかもしれません。バンス副大統領が現実になると、この争点を加速させる可能性が潜在的にあります。
また、トランプ支持を表明するより小規模なテクノロジー企業の経営者や投資家に対して、どのような政策がなされるかについては今のところ輪郭がなく、特段のリアクションをし辛いといえるでしょう。既にコロナ禍で高いバリュエーションで投資されたテクノロジー企業は政策で救えるとも思えず、どのような政策が効果的かつ支持者を満足させるか読みにくいといえます。
またトランプは7/18のインタビューで、半導体製造について台湾が米国から100%近いシェアを奪ったことを非難しましたが、この影響は中長期的には軽微ではないかと想定されます。半導体製造を米国内に完全に移すことはコスト面から合理性を見出すことは不可能ですし、設計分野は米国企業の独壇場であることを踏まえればどこかで折り合いをつけるでしょう。
金融業界全般
トランプ政権下では、金融業界全般に対して概ねポジティブな影響が期待されています。
前回のトランプ政権下での金融規制緩和の多くは実行に移されました。具体的には以下の通りです:
1. ドッド=フランク法の改正:
2018年に「経済成長、規制緩和、消費者保護法(Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act)」が成立しました。この法律は、ドッド=フランク法の一部を改正し、中小規模の銀行に対する規制を緩和しました。資産規模が500億ドル未満の銀行に対する厳格な規制が緩和されました。
2. ボルカー・ルールの緩和:
トランプ政権は、ボルカー・ルールの一部を緩和しました。2019年には、連邦準備制度理事会(FRB)や通貨監督庁(OCC)などの規制当局が、銀行が自己勘定取引を行いやすくするための新しいルールを導入しました。
3. 消費者金融保護局(CFPB)への制約:
トランプ政権下では、CFPBの権限が制限されました。例えば、CFPBのディレクターにミック・マルヴェイニーが任命され、消費者金融市場における規制の一部が緩和されました。これにより、消費者金融商品やサービスに対する規制が緩和されました。
これらの規制緩和の多くは、議会や規制当局を通じて実際に実行されましたが、すべての緩和策が完全に実行されたわけではありません。一部の提案は法案化されなかったり、完全な実施には至らなかったりしました。しかし、全体としてトランプ政権下での金融規制は大幅に緩和されました。
2024年に当選した場合、これらをさらに実行に進めると思われ、金融機関の収益を押し上げる可能性があります。
一方で、金利の影響も注視する必要があります。トランプが当選した場合、彼はFRBに対して低金利政策を求める可能性があります。しかしながら、彼の掲げるインフラ投資や大規模な減税が実行された場合、政府財務が悪化して、長期金利が上がる可能性があります。またトランプの貿易政策(関税の導入や貿易戦争のエスカレーションなど)が国際貿易に影響を与える場合、これが国内経済に波及し、金利政策に影響を及ぼす可能性があります。例えば、関税の影響で輸入物価が上昇しインフレ圧力が高まる場合、FRBは金利を引き上げるかもしれません。
暗号資産(仮想通貨)業界全般
トランプが暗号資産(仮想通貨)を支持しているのはこれまでの発言の通りです。
実際に法案になるとしたならば、以下のようなことが憶測されます。
● マイニング企業を支援して、新規ビットコイン(BTC)のマイニングを米国で行う
● 米政府による暗号資産の戦略的保有
● 暗号資産発行やアプリケーションの規制緩和
● ETF承認フローの軟化
● 暗号資産売却における減税
このように考えると、金融業界やテクノロジー業界はトランプが当選した場合、ポジティブとネガティブな影響それぞれグラデーションがありますが、暗号資産業界にとってはネガティブな要素が考えづらく、基本的に相当なポジティブなのではないかと思えます。
暗号資産にとってネガティブなシナリオを考えるならば、トランプが当選後、暗号資産に関する言及がすっかりなくなってしまい、目立った政策も行われなかった場合でしょうか。つまり暗号資産支援はあくまで選挙対策で碌な実行はされなかったというパターンです。この場合、それまで織り込まれた期待が剥落して、市場にダメージを与えるかもしれません。
しかしながら、可能性としてはそれは少ないように思え、筆者は楽観的です。トランプが暗号資産、とりわけビットコイン(BTC)を支持する・支持し続ける理由を憶測すると、暗号資産の市場規模は小さく、自身の影響を及ぼしやすいからです。加えて、ビットコインが過去と同程度の値上がりだとしても、それを自分の功績にしやすいこともあるでしょう。
そのことを考えれば、トーンが弱まったとしても、彼はある程度ビットコインを支持するのではないかと考えます。
総括
今回はトランプが当選した場合における影響を、テクノロジー業界全般・金融業界全般・暗号資産(仮想通貨)業界全般に対してシナリオ分けを試みました。
しかしながら、前提として、トランプの発言は強烈なだけにマーケットへの初動のプライスアクションが大きいこと、交渉スタイルはとても最初に大きいボールを投げて徐々に妥協案を模索するスタイルであることも頭に留めておくべきでしょう。その意味で右往左往することは悪い結果を招きやすいです。
本レポートの内容はあくまで執筆時点での見解であることを免責しておきます。
【ご注意事項】
本記事は執筆者の見解です。本記事の内容に関するお問い合わせは、株式会社HashHub(https://hashhub.tokyo/)までお願いいたします。また、HashHub Researchの各種レポート(https://hashhub-research.com/)もご参照ください。
提供:HashHub Research
執筆者:HashHub Research