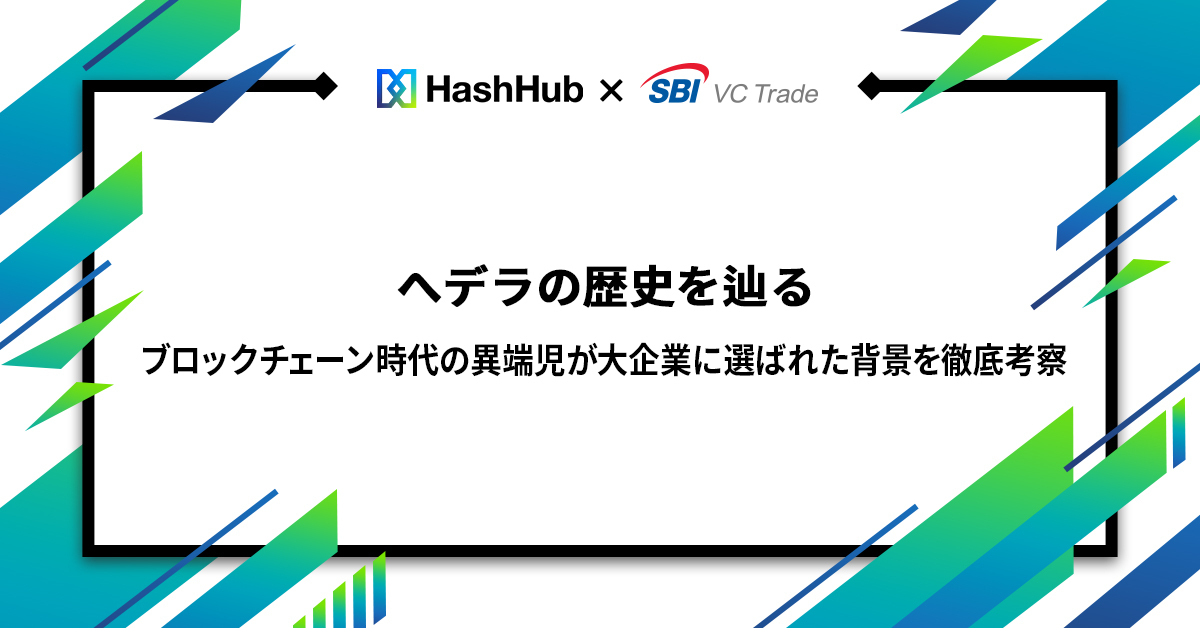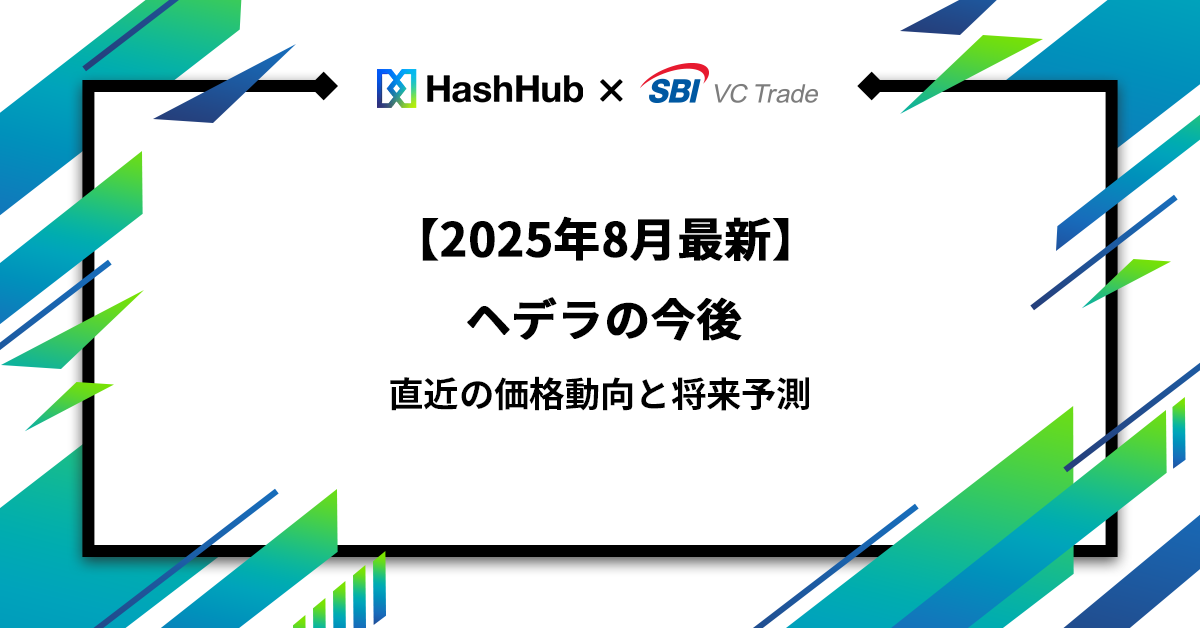▼目次
暗号資産(仮想通貨)ビットコイン(BTC)が世に出て以来、分散型台帳技術(DLT)の代名詞は常に「ブロックチェーン」でした。
しかし、その潮流に逆らうように独自の道を歩み、世界の巨大企業を次々と巻き込んできた異端児が存在します。
それが「Hedera Hashgraph(ヘデラ・ハッシュグラフ)」。
多くの批判と期待が交錯するこのプロジェクトは、一体どのような歴史をたどり、企業社会での地位を確立してきたのでしょうか。
その歩みを、中立的かつ批判的な視点から、暗号資産(仮想通貨)ヘデラ(HBAR)の市場価格への影響も踏まえつつ、深掘りしていきます。
【Hedera/ヘデラ参考情報】
- Website:https://hedera.com/
- ブログ:https://hedera.com/blog
- X:https://x.com/hedera
- Github:https://github.com/hashgraph
- エクスプローラー[hashscan]:https://hashscan.io/mainnet/home
ヘデラ(HBAR)黎明期:鳴り物入りの船出と「反ブロックチェーン」の思想(2018年)
ヘデラ(HBAR)は、リーモン・ベアード(Leemon Baird)とマンス・ハーモン(Mance Harmon)によってアメリカで設立されました。
ハッシュグラフアルゴリズムの発明者として知られるベアードは、コンピュータサイエンスの博士号を持ち、アメリカ空軍士官学校で研究科学者も務めた経歴を持ちます。
一方、CEOを務めるハーモンも、20年以上の起業経験を持つベアードの長年のビジネスパートナーでした。
彼らは共に2015年に「Swirlds, Inc.」を設立し、ハッシュグラフをプライベート向けに商業化。
後の2018年に「ヘデラ・ハッシュグラフLLC」を別法人として設立。この時点ですでに、ヘデラは技術的、そして経営的な面でも、しっかりとしたバックグラウンドを持つプロジェクトだったことがわかります。
(参照:https://hedera.com/journey)
ヘデラが初めてその存在感を広く示したのは、法人およびハッシュグラフベースのパブリックDLTのホワイトパーパーを公開した2018年のことでした。
同年、信用組合向けのブロックチェーンコンソーシアムであるCULedger(現:bonifii)が、国際送金にヘデラのパブリックハッシュグラフを利用する計画を発表。
このときから、ヘデラは「ブロックチェーンではないハッシュグラフ」というDAGに類似した独自技術を前面に押し出します。
当初彼らの技術は、オープンソースではなくSwirlds社の著作権ソフトウェアであり、ガバナンスも完全に分散型ではなく、最大39の国際的な信頼ある組織から成る評議会「へデラ評議会」を予定しているという、当時の暗号資産コミュニティの常識とは全く異なる姿勢を示していました。
同年8月には、メインネットをローンチし、公開分散台帳プラットフォームの開発資金として、機関投資家や富裕層などから1億ドルもの巨額を調達。
しかし、その船出は決して順風満帆ではありませんでした。
当時は活況だった暗号資産市場に対し、ヘデラのクラウドセールは認定投資家に限定され、未来のトークンを約束するSAFT(Simple Agreement for Future Tokens)という手法が採用されました。
さらに、創業者のトークンが4〜6年かけて権利確定されるという保守的な姿勢は、「反クリプト」とすら評されたのです。
自由と分散を是とするコミュニティとは一線を画す、その異質な哲学は、すでにこの頃から垣間見えていました。
同年12月には初のコミュニティテストプログラムを開始し、ハッシュグラフ技術が主張する高い取引パフォーマンスを実証するべく、テストや第三者アプリ開発に対して、独自トークンである暗号資産(仮想通貨)「ヘデラ(HBAR)」で報酬を支払う仕組みを導入しました。
この時点で、ヘデラは技術的優位性をアピールしつつも、そのガバナンスと技術の独自性で、すでに業界内外の注目と論争の中心となっていたのです。
企業が群がる「ガバナンス・カウンシル」の謎(2019年〜2020年)
ヘデラ(HBAR)の特徴を語る上で、そのガバナンス体制は避けて通れません。
彼らは、プラットフォームの安定的運営と企業利用の促進を目指し、「ガバナンス・カウンシル/へデラ評議会」という、最大39の信頼できる企業を集めた運営評議会によって運営される仕組みを構想しました。
これは、まるでVISAの設立初期をモデルにしたかのような、中央集権的でありながら多様なステークホルダーを取り込むユニークな試みです。
2019年2月には、ドイツテレコム、DLAパイパー、野村證券、スイスコム・ブロックチェーンAGなど、大手企業5社が最初のメンバーとして加わりました。
この発表は、ヘデラが単なるテックスタートアップではなく、既存の産業界に深く食い込もうとしている姿勢を示すものでした。
その後も、IBMとタタ・コミュニケーションズ(8月)、ボーイングと銀行ソフトウェア会社FIS(8月)など、名だたる企業が次々と参画を表明しました。
しかし、2019年9月にHBARトークンがローンチされると、暗号資産(仮想通貨)ヘデラ(HBAR)の価格は期待に反して低迷し、市場の評価は決して高いとは言えませんでした。
多くの投資家が様子見に転じる中、ヘデラは雌伏の時を過ごします。(図1参照).png?w=1075&h=849)
図1.ローンチから2020年末までの暗号資産(仮想通貨)ヘデラ(HBAR)の価格推移および7日間平均リターン推移の可視化
(出所:Coingeckoを元に筆者作成)
そのような中、状況を一変させたのが2020年2月、ITの巨人Googleが参画したことです(※同時期に次節に後述する「ヘデラ・コンセンサス・サービス(HCS)」も開始)。
このニュースは市場に強烈なインパクトを与え、ヘデラのトークン価格は数日で4倍に跳ね上がりました(図1参照)。
その後も、インドのIT企業ウィプロ(3月)、LGエレクトロニクス(5月)、クウェートの通信会社Zain Group(6月)などが加わり、ガバナンス・カウンシルの存在感はますます高まっていきました。
しかし、同年7月には、初期メンバーであったスイスコムが撤退するという異例の事態も発生しました。
これは、ガバナンス体制が完全に安泰なわけではない、という現実を突きつけた出来事でした。
へデラ評議会のメンバーは、ノードを運営し、プラットフォームのコード更新を承認する権限を持ちます。
このモデルは、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)のように不特定多数のマイナーや開発者にガバナンスを委ねるのではなく、信頼できる企業連合が安定的に運営することで、企業の利用障壁を下げようというヘデラの戦略が明確に見て取れます。
しかし、その一方で、「許可制」であるがゆえに、真の分散化とは言えないのではないかという批判も常に付きまといました。
ヘデラは、企業が求める安全性と安定性を手に入れる代わりに、分散型技術が持つ本来の理念をどこかで手放したのではないか、という疑念は今も晴れていません。
ヘデラ(HBAR)普及への胎動:現実世界でのユースケースと技術の拡張(2020年〜2023年)
華々しい資金調達と企業連合の形成を経て、ヘデラは次第に具体的なユースケースの模索へと舵を切っていきます。2019年9月にメインネット・ベータ版が公開され、多くのdAppが誕生したものの、この時点ではまだヘデラの真価は発揮されておらず、その将来性に大きな期待が寄せられる段階でした。
大きな転機となったのが、2020年2月に発表された「ヘデラ・コンセンサス・サービス(HCS)」です。
これは、ヘデラ独自のコンセンサスアルゴリズムを、外部のアプリケーションや他のブロックチェーンでも利用可能にするという画期的なサービスでした。
これにより、ヘデラは自らのプラットフォームに限定されず、他のエコシステムにもその技術を拡張する道を開きました。
このHCSの発表後、複数の実証実験が進みました。同年4月には、米国のクーポン管理団体がHCSを導入し、クーポンの不正防止と追跡に利用することを発表します。
そして6月には、広告会社のAdsDaxがインドのエンターテイメント企業との大規模なリアルタイム広告キャンペーンでヘデラを利用し、1秒あたり1,300件もの取引を達成したと報告しました。
これらの事例は、机上の空論だったヘデラ技術が、実際にビジネスの現場で活用できることを示す重要なマイルストーンとなりました。
その後も、ヘデラの技術は着実に進化を続けます。
2021年には、他のブロックチェーンとの相互運用性を高めるため、 Hashportというクロスチェーンブリッジを立ち上げました。
さらに、IPFSのような分散型ストレージシステムであるFilecoinとの連携も発表し、Hedera上のNFTメタデータをFilecoinへ分散保存するSDKやデモを支援する取り組みを実施。
同年には、プロジェクトのガバナンスをより透明化するため、コミュニティ主導で提案・議論を行う「ヘデラ改善提案(HIP)」を導入するなど、創業当初の「反クリプト」的な姿勢から、少しずつコミュニティとの協調路線へと歩みを進めているようにも見えます。
この時期、2021年9月中旬にはHBARトークンが0.5ドルを上回る歴史的最高値に達し、市場からの大きな期待を証明しました(図2参照)。
図2.2020年〜2021末までの暗号資産(仮想通貨)ヘデラ(HBAR)の価格推移およびリターン推移の可視化
(出所:Coingeckoを元に筆者作成)
しかし、2022年に入ると、ヘデラは大きな転換点を迎えます。
この時期、暗号資産市場全体が下落基調に転じ、ヘデラもその影響を免れることはできませんでした。
ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)に連動しつつも、相対的にアンダーパフォームする時期が続きました(図3参照)。
価格が低迷する中、ヘデラはハッシュグラフアルゴリズムの知的財産権を買い取り、オープンソース化することを決定します。
これは、かつて「独自技術」としてクローズドだった技術をコミュニティに開放するという、大きな方向転換でした。
同年第2四半期には、ヘデラの製品開発チームがSwirlds Labs(現:Hashgraph)に移管され、創業者であるベアード氏とハーモン氏も加わって、ヘデラ上での未来の構築を加速させるミッションを担うことになりました。
これにより、ヘデラ評議会はガバナンスとネットワーク運営に、Hashgraph社は技術開発に専念するという分業体制が確立されたのです。
図3.2022年〜2023末までの暗号資産(仮想通貨)ヘデラ(HBAR)の価格推移およびリターン推移の可視化
(出所:Coingeckoを元に筆者作成)
2023年に入ると、新たな実証実験が次々と報じられます。
韓国の新韓銀行とタイのSCB TechXがヘデラネットワーク上でステーブルコイン送金の実証実験を成功させ、金融分野での活用可能性を強く示唆しました。
さらに、デル・テクノロジーズやCOFRAホールディングといった新たなメンバーが評議会に加わり、その影響力はますます強まっていきました。
これらの事例は、価格低迷期にあっても、ヘデラが着実に現実世界でのユースケースを積み重ねていたことを示しています。
ヘデラ(HBAR)転換期:金融業界への本格参入と現実世界の改革(2024年〜2025年)
そして、ヘデラの歴史は新たな段階へと突入します。
2024年に入ると、その技術はより大きなスケールで利用され始めました。
特に、米国大統領選挙を境に暗号資産市場全体が活況を呈する中、HBARトークンはビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)を上回るパフォーマンスを見せ、停滞期を乗り越えたその技術的優位性を市場に証明しました(図4)。
図4.2024年10月〜2025年8月現在までの暗号資産(仮想通貨)ヘデラ(HBAR)の価格推移およびリターン推移の可視化
(出所:Coingeckoを元に筆者作成)
この時期、サウジアラビアの投資省と「DeepTech Venture Studio」を立ち上げ、中東での影響力拡大を図る動きが見られました。
また、日本の日立アメリカがヘデラ評議会に加わり、産業用途での概念実証に着手するなど、アジアでの展開も活発になります。
さらに2025年には、ヘデラの評価を決定づけるような大型案件が続々と報じられます。
まず、オーストラリア準備銀行が進める卸売中央銀行デジタル通貨(CBDC)の実証実験において、ヘデラの公共ネットワークが利用されたことが明らかになりました。
これは、国家レベルの金融インフラにヘデラが活用される可能性を示す、極めて意義深い動きです。
そして同年、英国のロイズ銀行とアバディーン・インベストメンツが、ヘデラ上でトークン化された担保を外国為替(FX)取引に活用した事例が報告されました。
これにより、従来は非効率だったデリバティブ取引における決済の遅延が解消され、資産の即時移転が可能であることが実証されました。
また、ヘデラの技術基盤とガバナンスの中核を担うHashgraph(旧Swirlds Labs)は、企業向けの許可型DLT「HashSphere」の立ち上げを発表しました。
これは、パブリックDLTでは対応が難しいプライバシーやコンプライアンス要求に応えるものであり、企業が安全かつ柔軟に分散台帳技術を活用できる環境を提供するものです。
こうした取り組みにより、ヘデラはオープンなパブリックネットワークとしての進化を続ける一方で、企業ニーズに応じたプライベートソリューションも展開するという、二軸の戦略を明確に打ち出した形となっています。
結び:異端児ヘデラ(HBAR)の未来
ヘデラの歴史は、ブロックチェーンとは異なる道を歩み、独自性と妥協を繰り返しながら、着実にその地位を築いてきた軌跡といえます。
オープンソースの精神とは相容れない独自技術と、分散化とは矛盾するへデラ評議会。その異端ぶりは、常に批判の対象となってきました。
しかし、皮肉にも、その「管理された分散性」こそが、厳格なコンプライアンスや安定性を求める大手企業にとって魅力的に映ったのかもしれません。
暗号資産(仮想通貨)のビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)がボラティリティやガバナンスの問題に揺れる中、ヘデラ(HBAR)は着実に企業との関係を深め、現実世界でのユースケースを積み上げてきました。
コードのオープンソース化やコミュニティへの寄贈など、創業当初の「反クリプト」的な姿勢から脱却し、より多くのステークホルダーを取り込もうとする姿勢も見られます。
ヘデラが本当に「未来の分散台帳」となり得るのか、それとも単なる「企業の都合の良いツール」に留まるのか。
その答えは、これから彼らがどれだけ多くの実用的なアプリケーションを生み出し、真の価値を証明できるかにかかっています。
異端児ヘデラの挑戦は、まだ始まったばかりです。
【ご注意事項】
本記事は執筆者の見解です。本記事の内容に関するお問い合わせは、株式会社HashHub(https://hashhub.tokyo/)までお願いいたします。また、HashHub Researchの各種レポート(https://hashhub-research.com/)もご参照ください。
提供:HashHub Research
執筆者:HashHub Research